音程をどうとるか…生きる
前回、生きるということは繊細でいていい加減なものと書いた。そして、生きるということは感じるということにほかならないと言った。何年も前に「虎落笛」や、「ネアンデルタールの笛」で書いたように人類が音楽を手にしたのは、まさに生きていて、感じたからに他ならない。理論に従ったわけでもなく、計器に示されたからでもない。次の譜面を見てみよう。
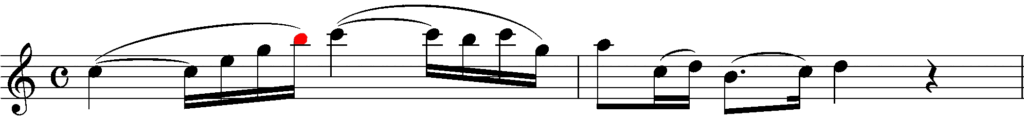
ヘンデル フルートと通奏低音のためのソナタハ長調 第1楽章 HWV365
この赤い十六分音符をどのような音程で吹くか何回も試してみてほしい。まずはフルートだけでだ。どうだろう?何でもありじゃないか?喜びに満ちていたり、希望に溢れていたり、悲しくも吹けるし、豪華絢爛にも、鬱々とした気分に合わせても吹ける。それが生きてるってことなんだ。この時、このシを平均律で吹くべきか、純正律で吹くべきか、そのどちらか決めなきゃならないのか?それをチューナーで確かめりゃいいより良い音楽になるのか?それっていかにも貧しくはないか?さらに、この曲の通奏低音は
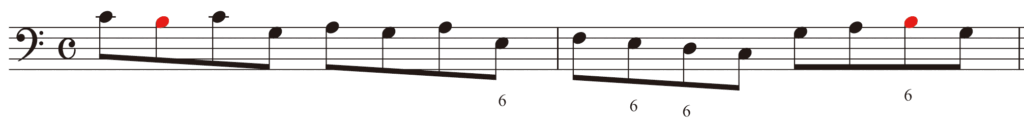
こんな風になっていて、最初の赤い音符シが心配だよな。そして、こんな伴奏が付けられていたりする。
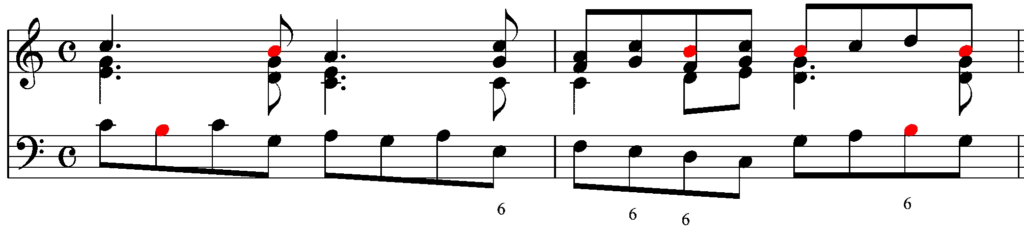
これ、普通は鍵盤楽器で伴奏するから、ピアノだったら平均律だし、チェンバロだったら調律法でいくらかの融通が利くだろうが、音程は動かせない。だから、低音の最初に出てくる赤シに支配されちゃうんじゃないか、右手のシと衝突するんじゃないかと・・・気にしないでやってみな!おかしくないだろ?
無表情で、ただ伴奏の鍵盤楽器のシに音程合わせたって、意味がないどころか、シんじまうわ。
通奏低音部分は変えられないが、伴奏の右手部分は、伴奏者の自由だから余程の不都合、モロにぶつかったりしたら、伴奏の部分を変えてやればいいんだ。この部分はヘンデル親分が好きにしてくれと言っているんだから。せっかくフルートを吹いているんだ、音程を自由に変えられる楽器なんだから、旋律を取り戻せ!と言いたい。
もう一つ例題だ。これを何回も吹いてみてくれ。ハ長調のラシドシラだと想定して吹いてみてくれ。次にイ短調のラシドシラだと思って吹いてみてくれ。
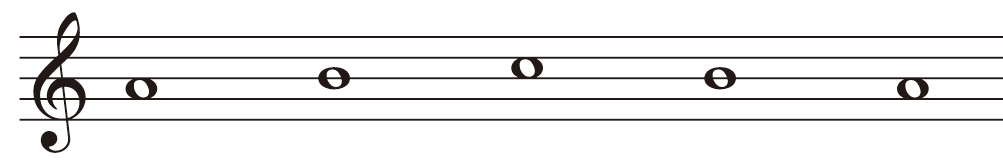
これな、たとえ純正律であっても計算上は長調も短調も同じ音程のはずだ。しかし、短調の場合、音程を狭めていくとどんどん陰鬱な気分になれるよな。この時点において、明らかに「ド」の音程を動かさなきゃならない。ハ長調なら「ド」は動かさないほうが良いだろう。
あらゆる局面で、このように旋律を我が物にできるかどうか、これがフルートを退屈にしないひとつの方法だろう。直ぐにチューナーを譜面台から降ろそうぜ。でもゴミ箱には入れるなよ。それなりの使い道はあるから。でもなぁ、おいらが学生の頃、チューナーは高かったぞ。誰もが持っているという代物ではなかったぞ。チューナーが普及して、音楽が面白くなったか?練習が効率よくできるようになったか?上達が早くなったか?アンサンブルが美しく揃うようになったか?
しつこく言う。生きてるんだから感じろ!
今日はここまでだ。キッチンからいい匂いがしてきたからな。今日はカミさんの料理なんだ。

コメントを書く