難しい指使いの練習方法(1)
前回までに、間違えないで吹けるテンポからゆっくりさらうこと、音符をかたまりで読むことを述べた。とはいっても、難易度はテンポや楽譜の複雑さだけで決まるわけではなく、やっぱり「うまく動かねぇな」という単純に指の動きが問題になるケースがある。こんなときどうするかが、今日のテーマだ。
楽譜を合理的に捉えること、つまり、重複部分は省き、似ている部分は差分を取り、連なる音は音階なのか、分散和音なのか、装飾なのか、簡単なアナリーゼをして(正しくなくていい)かたまりで認識する・・・それでもまだ練習には時間がかかってしまうもんだ。よし、もっと合理化だ。
毎度突っかかる部分とか、「なんとかできたけどイヤ~なところ」が当然あるだろう。そこで、<どこがどのようにできないのか>を煮詰める。「だいたいこの辺」じゃぁだめだ。どの音と、どの音のつながりの悪さが、どの指の動きの悪さによって起こっているのかを徹底的に分析するんだ。ある二つの音が特定できればそこだけを解決する。あるいは三つの場合もあるだろうし、四つの場合もあるだろうが、せいぜい四つくらいまでに特定したほうが良い。観察!観察!観察!
この不具合の発生する部分を特定出来たら、もう半分は成功だ。機械の修理だって不具合部分が特定できなきゃ成果はゼロだ。で、そこをどうやって改善するかの方法だ。こんな時はメトロノームなんかメンドクサイので使わない。特定された音が二つなら3連符、三つなら4連符四つなら3連符の輪を作る。それをゆっくりから始めだんだん速くし、まただんだんゆっくりしていって終わる。大切なことは、
①ゆっくりから始める
②コントロールが効かなくなるほど早くしてはいけない
③一番早くなった頂点は全体の中間になるようにすること
④初めのテンポと終わりのテンポが同じになること
⑤一息いっぱいを全体の長さにすること(途中で息はとらない)
これでやってみてくれ。下に譜例を挙げておく。
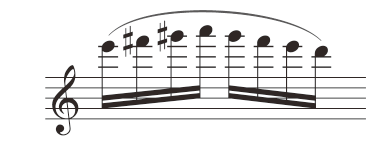
こんなところが上手く吹けなかったとすると・・・
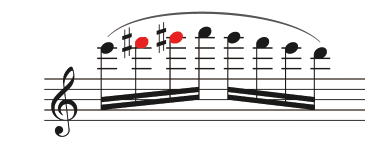
原因がこの二つの音だったら・・・
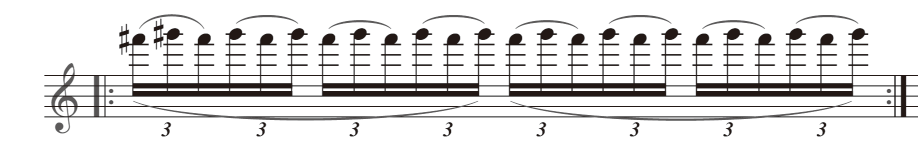
この音型で繰り返す
ゆっくり始め、何度も繰り返していく中でだんだん速くする、コントロールが効く範囲でできるだけ速く吹く。そしてだんだんゆっくりしていって最初の速さに戻る。
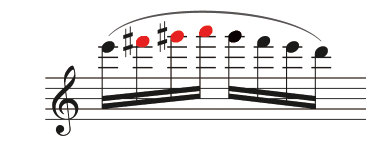
原因がこの三つの音だったら・・・
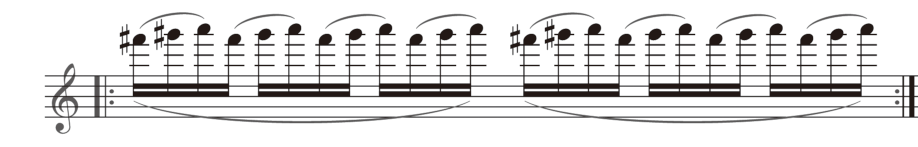
この音型で繰り返す
ゆっくり始め、何度も繰り返していく中でだんだん速くする、コントロールが効く範囲でできるだけ速く吹く。そしてだんだんゆっくりしていって最初の速さに戻る。
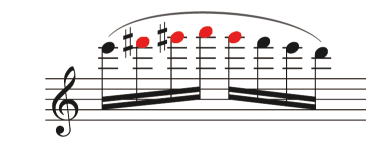
原因がこの四つの音だったら・・・
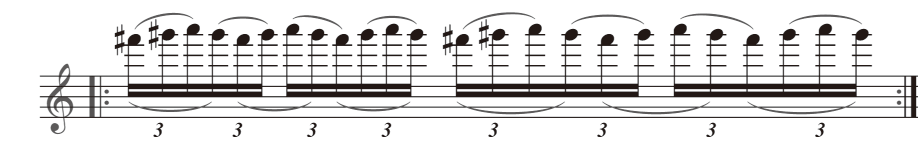
この音型で繰り返す
ゆっくり始め、何度も繰り返していく中でだんだん速くする、コントロールが効く範囲でできるだけ速く吹く。そしてだんだんゆっくりしていって最初の速さに戻る。
音型とアーティキュレーションと拍節をわざとずらしてあるだけだが、このことによって毎回、力点が動く。これがコツだ。だから慣れないうちは軽いアクセントを拍の頭に置いても良いだろう。
今日はここまでだ。おや、鶯が鳴いている。

コメントを書く