中級者向き、エチュードの吹き方(4)
エチュードをたくさんやると、何がいいのかって言うと、前にも書いたと思うけど、「譜読みが早くなる、譜面がよく読めるようになる」という効果が一番大きい。譜読みが苦手な人の特徴は、音符の玉(符頭)をひとつ一つ追っかけていくので、これで早いパッセージを吹こうとするなら、動体視力の勝負になってしまう。譜面を素早く読むには、「塊で読む」「パターンで読む」ことに慣れてしまう以外にない。演奏中、脳の中に音符認識というテーブルを拡げる。このテーブルに、音符を一つずつ置いて解釈していったら忙しくてしょうがない、あっという間に脳のCPUはパンクする。このテーブルの上にできるだけたくさんの音符をバァっと拡げて、一度に認識してやるんだ。これがコツ。間違えないようにゆっくりから練習するというのは、動体視力を鍛えるのではなく、最初はひと粒ずつしか認識できなかった音符を、次第にいくつかの塊として認識していけるようにするのが目的だ。そして、どのように塊を認識すれば良いのかが大切なんだが、次の譜面を見てほしい。
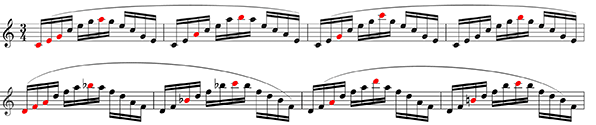
Joachim Andersen Op.15 24Große Etüden für Flöte Nr.1
数回の練習の後、パターンが認識できれば、この楽譜の赤い音符だけ見ていけば吹けるだろう。と、すると、一瞬で一小節分くらいは認識できるはずだ。確か前回に、「差分を認識する」と書いたと思うが、これがその一例である。また、こうすると頂点にある旋律線がちゃんと見えてくるので、表現の上でも役に立つだろう。(1段目のラ・シ・ド・シ、2段目のシb・ド・レ・ド)
そしてここで大いに役立つのが、みんな大好き「楽典」の知識と、「基本練習」の成果だ。上記の譜面で言うと、ハ長調、イ短調、ニ短調、変ロ長調、減七の和音が出てくる。これらのアルペジオ練習をもし普段からやっていたとすれば、大いに役立つはずだ。余談だが、減七の和音は3種類しか存在しないのだが、それだけを取り出して練習されることはめったにない。しかし、エチュードには頻繁に出てくる。やり方は先生に相談してね。
では、こんな譜面はどうだろう。
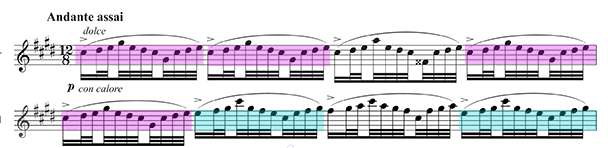
Joachim Andersen Op.15 24Große Etüden für Flöte Nr.10
この譜面の背景に色がついている部分は全く同じだ。こんな時、眼を真っ赤にして音符一つずつ見ていったら⚪︎ホだぞ。
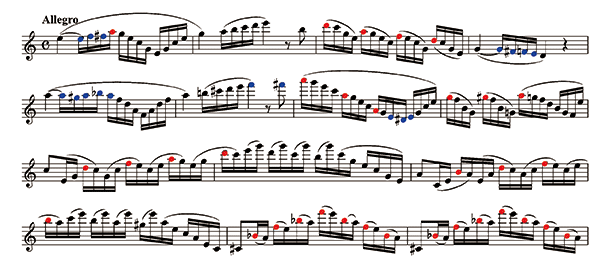
Ernesto Köhler Op,33-2 Nr.1
譜面に書き込んである赤玉は全部全打音だ。当たり前だが、次の音は2度下で、これを省いて譜面を見りゃ、何のことは無いドミソの和音だったりだラドミの和音だったりする。そして、青玉から次の青玉までは半音階だ。パッと見て半音階だと分かれば、半音階を吹けばいい。臨時記号に惑わされてはいかん、そんなもん見ない。始点と終点さえ分かれば見なくていい。だから、半音階も日頃練習している人は有利だね。ついでに言うと、2段目の3小節目のミ・レ#・ミはモルデントだ。こんな時「え~と、レのシャープだから・・・」なんて考えてたら置いてきぼりを食らう。臨時記号が出てきたついでに言うと、ある臨時記号が「転調したから」出てきたのか「単に経過音や、装飾的な意味」によって書かれているのかを把握しておくと良い。転調していれば、その部分の記号(#がいくつとかbがいくつだとか)を頭に展開すればいいし、装飾的な意味として付いているなら前後の音はたいてい半音上か下だ。それから短調だと6度と7度には臨時記号が付きやすいし・・それでねダブルシャープなんか出てきた時に、「え~と、ファのダブルシャープだから、ファ#でもう一個上だからソだな」なんて考えていたらまずアウト!ましてや、楽譜にカタカナなんかでフリガナ振ってたりしたら、中級レベルとしては、上達は「望み薄」だよ。もしまだやってたら、すぐに止めてね、大丈夫だよ、すぐにできるようになるから・・・と優しく注意しておくよ。
今日はここまでね。か・た・ま・りで読むんだからね。

コメントを書く